沖縄総合事務局主催の 「跡地利用推進セミナー」 に参加したので個人用のメモしておきます。
今回の講師は官僚の古谷雅彦氏でした。
セミナーの案内を見た当初、失礼ながら存じ上げていませんでしたが、ツイッターのフォロワーさんから事前に情報をいただいていました。
古谷雅彦氏は、前回の沖縄特措法改正時の内閣府沖縄振興局総務課長です。沖縄に精通した方ですよ。(^^) https://t.co/Ot2CuyW7nJ
— rの住人 (@JH9T2oMRrGYXs0A) December 18, 2019
事前情報のとおり、沖縄県民以上に沖縄のことに精通していました。
色々と裏話を交えた興味深いお話しを1時間したあとに、「今回の内容は財務省などの組織や官僚としての意見ではなく私(古谷氏)個人の意見ですので」とおっしゃっていました。
参加者は約30人くらいでした。受付用紙をチラ見したところ、県の各担当部局や市町村職員などの行政職が多数です。
今回のセミナーは行政以外に土地連にだけ広報していたようで、土地連からの案内でしょうか?という質問がありました。ということで、行政職以外には軍用地主などの一般人が4~5人という感じの雰囲気でした。

皆さんスーツにしっかり名札を付けており
アウェー感が強かったですねw
今回のブログは、古谷氏の個人的意見に僕が軍用地投資の視点で感じたところをだけをメモしていますので、あくまでも参考程度、いやただの読み物として流し読みする程度でお願いします。
それでは行ってみましょう!
沖縄の特殊事情と沖縄振興の仕組み
跡地利用のお話しに入る前に沖縄の特殊事情と、これまでとこれからの沖縄振興についての説明がありました。
沖縄は日本本土と比べると特殊な環境と言われていますが、主に以下の3点です。

それに対する国の責務として沖縄振興が図られてきました。

こんなにもあるのかと思うほどの沖縄振興が図られているのが分かりますね。

正直言って知らないことが沢山ありました(;´・ω・)。
手厚い待遇だったというのがデータで紹介されていました。
この手厚い沖縄振興の根拠が沖縄振興特別措置法です。
この法律は、沖縄振興開発特別措置法(昭和47年5月~平成14年3月)として沖縄返還と同時に時限立法として施行され、その後2度の期限延長を経て、沖縄振興特別措置法(平成14年4月~平成34年3月)になりました。
その沖縄振興特別措置法の期限があと2年と迫っています。

これまで本土との格差是正を念頭にやってきましたが、実際のところ格差是正はほとんど終わっており、これからは民間主導の自立型経済の構築を目指すこととなっています。
これまで ⇒ 本土との格差是正
これから ⇒ 民間主導の自立型経済の構築
沖縄が本土並みの生活をするため国は沢山の資本を沖縄に投下してきましたが、計画・整備中のものを含めれば本土並みの整備(病院、港湾、道路、ダム、空港、水道、農業、学校)がと整ってきていると言えます。(基地問題は依然継続中)
その中から水道を例にとってみましょう。

この図は水道普及率と給水制限(断水)の日数を表しています。平成の初めの方から水道の普及率は100%で、その後ダムも沢山建設されてきました。そういえば、断水なんて長いこと記憶にありませんよね(‘ω’)
沖縄の戸建て住宅の屋根には水タンクが載っていましたが、最近の新築住宅では見られなくなっています。水タンクは断水になった時のために設置されていたのですが、最近では必要性があるのか分かりません。インフラが整備され生活が豊かになったということがよく分かりますね。
関係資料はコチラ(社会資本整備の実績と現状について)
特殊な事情を考慮した特別措置による沖縄振興から半世紀が経過します。この間に本土との格差是正はかなり進み、本土との遠隔性の問題が逆にアジアに近いこで優位性となっています。
講師のメッセージを僕はこう捉えました。 「沖縄県のハンデはまだ残っているものの、それを言い訳にするほどの状態ではなく、県民自らの主体的に行動すべし!」
跡地利用
続いて跡地利用のお話しに入りますが、その前におさらいです。
嘉手納飛行場以南の基地返還について、軍用地に興味を持っている皆さんならご存じだと思いますが、改めて確認しておきましょう。

この図にある基地全てが今後10年以内に返還される予定です。(普天間飛行場はモメていますが)。前回の西普天間住宅地区に続き、2020年3月でキャンプ瑞慶覧の一部も予定通り返還され、軍用地主が単純計算で140人減ります。

このように返還に向けて準備は着々と進んでおります。
この図から分かるように、10年以内に大規模かつ広範囲で基地が返還され、跡地利用問題が発生するということが分かりますね。最近の返還地はイオンモールライカムやパルコシティなど大型のショッピングモールが作られたり、マンションホテルの建設が進んだりと、基地返還後の跡地利用はバラ色に見えましたが、これからはどうも雰囲気が違ってきそうです。
というのも、いま以上にマンションやホテル、大型ショッピングモールを作ればお互いの消耗戦がめに見えており、結果的に沖縄全体の発展が阻害される可能性が高いからです。
大規模な土地が返還されれば県外の資本が入ってきた土地を買い上げたり、賃貸契約になって何とかなるだろうと浅い考えでしたがもはや過去の話かもしれません( ;∀;)

僕も跡地利用について楽観的でしたが、
そう簡単ではないことは分かりました。
これ以上ショッピングモールはいりませんし。
ちなみに、キャンプキンザーや那覇軍港は重要な位置にあるにも関わらず、これといった案が全く出ていないとおっしゃっていました。(県や市に対する重大なメッセージ)
最近の跡地利用事例として、キャンプ瑞慶覧の西普天間住宅地区のお話しもありました。ご存知の方が多いと思いますが、西普天間地区には国立の琉球大学医学部・病院の移設が決まっています。
これまで土地を使いたくても使えない地主に対して、返還後も基地跡地を国が使う(琉大病院は国立)ため、賃貸契約の継続ではなく、買い上げる方針にしたそうです。
当然ですが、基地返還後の土地をどう活用するかは地主の仕事なのでそこは地主さんがしっかり汗をかいてくださいと言っていました。

再三にわたって、県民や市町村が主体性を持って取り組む必要性を訴えていました。
まとめ
沖縄県は変革期を迎えており、今後本格化し始める基地の跡地利用は大きな課題になりそうです。
地主さんはもちろんですが、沖縄県や各市町村が本腰で取り組まないと悲惨な結果になる可能性があります。これまで音頭をとってきた国の現状はご存知のとおりです。少子高齢化により人口減少が続いています、社会保障制度などから分かるように財政はより一層厳しくなるでしょう。そんな中、私たち一人一人が知恵を絞っていかないといけません。
強制的に土地を接収された先人にとっては、土地の返還をもって一つのゴールかもしれません。
しかし、軍用地投資として参入した私たちにとっては基地返還が今後の資産運用を左右する重要なポイントになりそうです。跡地利用を主導する国や県かもしれませんが地主の方が当事者です、自ら考え行動するよう心掛けたいですね。
おまけ
今回配布された資料ですが、結構いい資料がそろっていたので探せただけでもデータ貼っておきます。ご活用下さい(^^♪

- 半世紀を迎える沖縄振興の今後の在り方について(平成28年11月17日)
- 社会資本整備の実績と現状について(平成28年6月8日)
- 沖縄振興の仕組みについて(平成28年6月8日)
- 沖縄の振興について(令和元年6月14日)
こちらの記事も一緒に読んでみてください。
2019年に軍用地跡地利用特措法について書いた記事です。


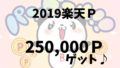
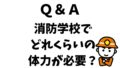
コメント