日本の人口は今年も順調に減少しました。この流れはいつか止まるのでしょうか。
聞いた話ですが、少子化対策に本気で取り組もうとする政治家は高齢者から票が取れず、選挙に勝てな、、、な、、なんでもありません。
そこで不平不満を言ってもどうにもなりませんから、今できることは、現状を踏まえてどう行動するかですね。
現状を俯瞰してみることで、正しい準備ができるのではないでしょうか。

2020年1月1日時点の住民基本台帳人口は、前年から日本人住民が50万減少し、外国人住民が20万人増加して、1億2713万人8033人となった。2009年をピークに日本は人口減社会に突入しているが、日本人人口の減少幅が50万人を超えるのは初めて。そのインパクトを分かりやすく表現するとすれば、鳥取県の人口56万1175人(日本人+外国人)に近い人口が消滅したことになる。
将来の予測なんて意味がないと言われそうですが、悪い想定をしておくのは重要なことだと思います。
新型コロナが出始めたころ、誰もこんなことになるとは思っていませんでしたよね。

僕もすぐ終息するだろうと思ってましたし。
これらの出来事で、我々消防業界にも大きな変化がありそうです。今のところ僕の妄想ですが、心の準備はしておきたいですね。

ということで、個人的な業界の予想を
書いてみたいと思います!
消防広域化など再編加速の可能性
人口減少で一番心配なのは、国の経済的成長が止まることです。
日本の人口減が、必ずしも国力衰退につながるわけではありませんが、可能性は低くないと思います。
そうなると、財政力指数の低い市町村はピンチになりそうです。
というのも、財政力の低い市町村対しては、国が交付金を配ることで財政不足を補い、公平性を維持しているのですが、国が衰退すれば、、、
財政力指数(ざいせいりょくしすう)とは地方公共団体の財政力を示す指標として用いられる指数であり、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値である。
財政力指数が1.0を上回れば、その地方自治体内での税収入等のみを財源として円滑に行政を遂行できるとして、地方交付税交付金が支給されない不交付団体となり、下回れば地方交付税交付金が支給される交付団体となる。したがって、地方交付税交付金が地方公共団体間の財政力の格差を調整するために支給されるものであることを踏まえると、その性質上必ずしもすべての地方公共団体に地方交付税交付金が支給されるわけではない。
ちなみに、多くの自治体が交付金の交付団体であり、国からの交付金にお世話になっています。

交付金を受け取っていない優良な?
自治体はこれだけしかありません。

ちなみに、自治体数って全国で約1700くらいあるみたいですよw
国から交付金をもらっている自治体に対して、「大人からお小遣いをもらっている子供のようだ。」という痛烈なコメントをしている専門家もいました。

だいぶ辛口ですが、
ぐうの音もでません。
ちなみに、新型コロナでさらにダメージを受けた自治体も少なくないようです。
想定超えてたよ。https://t.co/mSjQoQ4V0A
— P副隊長@ハブマン特掃係 (@motetagariya) November 29, 2020
今後の日本の実情を踏まえると、少子高齢化に伴って、社会保障費が増え、税収は減るという負のスパイラルとなって、ジワジワ消耗すしていくのは、みんな知っていることでしょう。

そうなると、これまで人口で日本を支えてきた制度などが通用しなくなるわけです。
当然、消防の組織再編も必須項目でしょう。
それを見据えたのか分かりませんが、市町村合併特例法も今年(2020年3月)に10年延長されています。
興味のある方はコチラもどうぞ(市町村合併についての今後の対応方策に関する答申)
我々消防業界にもしっかりと通知が出ています。
市町村の消防の広域化に関する基本指針の一部改正について(通知)平成30年4月1日
消防力の整備指針の一部改正について(平成 31 年3月 29 日)
関係通知を見ていると大まかな流れが分かってきますね。
消防広域化については、一時期活発に議論が行われていましたがこれからは財政の理由から広域化せざるを得ない消防が増えてくると予想しています。今後10年以内で大きな変化がありそうな予感です。

怒らないでくださいね、
あくまでも僕の妄想ですから。
救急業務がなくなる可能性
消防って赤い車のイメージが強いと思いますが、実際は救急業務の割合がぶっちぎり多いです。昭和38(1963)年に消防法に救急業務が明記されてから増加を続けています。
きれいな右肩上がりですね!



これが資産運用のチャートだったらw
参考までに、平成30年中に日本の対応した災害出動件数の内訳です。
| 平成30年中 | |
| 救急 | 660 万8,341 件 |
| 救助 | 6万1,507 件 |
| 火災 | 3万7,981 件 |

救急は火災や救助に比べて、
100倍~200倍の差があるんですね。
うちの署も同じような比率でした。
この統計から各地の消防で救急業務の過酷さが伝わってくると思います。
過去に救急・救助の事務を担当していた時期がありましたが、毎年増え続ける救急関係予算に頭を悩ませていました。

消防の仕事は救急だけじゃないんだけど。。。
と思いながらも救急業務に沢山の予算を使っていました。
話は変わりますが、コロナ渦になって高齢者の病院受診が減ったというニュースが流れました。
今年(2020年)5月の医業利益率は、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた病院では「マイナス13.6%」、一時的に病棟を閉鎖せざるを得なかった病院では「マイナス14.3%」の赤字となり、受け入れていない病院でも「マイナス8.3%」の赤字に陥っている―。
友人の病院スタッフは2020年の夏冬のボーナスがカットになったそうです。
現行の医療について意見を言える立場ではありませんが、人口が減ることで病院の経営も苦しくなるのではないかと思っています。
改めて日本の人口推移を見ておきましょう。


今この急激な下り坂の始まった所です。w

人口が少なくなると同時に病院もスタッフさんも上手く縮小していければいいのですが、うまくいくのでしょうか。
病院も生き残りをかけて患者さんの獲得に身を乗り出してくるのではないかと思います。
最近ではドクターカーの普及が顕著です。現場まで医師・看護師が来て救急隊と一緒に活動します。
少し乱暴な言い方になりますが、医師が現場に来ることで救急隊が処置を行う救命処置件数は減少しています。
当然ですよね、その場に医師や看護師が居るわけですから。
救急隊は救命処置ではなく、現場のマネジメントを行うのが主な活動になったりするわけです。
仮にこの流れが主流になったとしたら、消防が救急業務を行う必要性が問われる時代がくるかもしれませんね。
消防(行政の予算削減)、医療機関の患者さん獲得、高度な処置を早く受けることができる患者さん。
これ三方よしではないでしょうか。
実際に民間救急の会社も立ち上がっています。
これからの日本を考えると非常に安定性と成長力のあるビジネスだと思います。上場してるなら投資したいくらいです。
今のところは、消防非常備の地域が主ですが、救急業務が大転換を迎えようとしているかもしれません。

消防法(救急業務)や救急実施基準の見直し議論
が始まるのも時間のも時間の問題かも、、、
AI・ロボが大活躍する時代
人口が減少していく中で、効率よくAIなどに仕事を任せていけばいいのですが、それ自体が仕事を奪うかもしれないと騒がれていて、何だか変な感じです。
時代の変化に合わせて我々も変化するべきで、AIで失われる仕事があれば、AIによって生み出される仕事もあるわけで。。。
その頃の我々の活動はどう変化していくのでしょうか。
公務員全般に言えることとして、大部分の仕事がAIで代替可能と言われています。
僕が過去に担当していた係の仕事は内容を思い出してみても、統計や前年踏襲の調査を繰りしていたので、9割がAIで代替できるのではないかと思います。
それに比べて、災害対応する現場の仕事がなくなるのは最後の最後だと思ってます。
当然、AIは実働側ではなくて頭脳の方ですから、現場の労働にはロボットが必要になってきます。
実際に、ロボの開発は盛んに行われています。
現時点では、主にコンビナートやプラントなどの大規模な災害現場に対応するものが主流ですが、今後は街中の災害にも使えるような小型で優秀なロボが出てくるでしょう。
そんなロボが現実的に購入できる金額になると仮定した場合、危険を伴う消防の仕事で、毎年殉職者がでる現実を考えればロボットの導入は当然の流れではないでしょうか。
大分ざっくりですが、職員一人当たりの生涯年収をみてみましょう。
極端な話ですが、この生涯年収の半分くらいの金額で有効なロボが買えるとなれば、、、人じゃなくてロボでいいじゃん?となりそうです。
いや、前線は人間じゃなくてロボにしようよ。という感じになるでしょう。
技術進歩は目まぐるしいので、実現されるはそう遠くないと思います。
消防団員の増
組織として消防本部と消防団は肩を並べています。

消防職員は公務員ですから、人数を増やせば増やすほど自治体の財政に影響を与えます。今のところ給与毎年上がっていきますし、リストラもできません。
ですので、効率よく地域の防災力を高めよと思うなら、非常勤の消防団員の存在は欠かせません。
消防団員は普段は本業の仕事を行いながら、災害時に消防団員として活躍されます。
そんな消防団員の減少が問題になっています。
下のグラフでは職員(赤)と、団員(青)の数を比較しています。
消防職員が増加傾向にあるのに比べて、消防団員は減少傾向が続いています。

首都直下型地震、南海トラフなど、大災害への危機意識が高まる中で、地域に根差した活動を行うことができる消防団員の存在は絶対欠かせません。
当然、国も動いています。
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律等を整備し、団員の減少に歯止めをかけようとしています。

地域防災の観点からは、やはり消防職より消防団員を増やす方が総合的に理にかなっていますので、今後も消防団増員への処遇改善などが続きそうです。

災害大国日本、
消防団員の増員は命題と言えるでしょう。
まとめ
僕が現段階で描いているの個人的な妄想記事を書いてみました。
妄想がどれくらい当たるのか楽しみでもありますが、変化に柔軟に対応すれば決して悪いことにはならないと思っていますが…
僕個人としては、どんな時代になっても生き残れる気がしていますので、どんな未来が待っているのか楽しみにしている所です。
こんな記事も書いています。





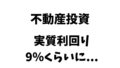

コメント